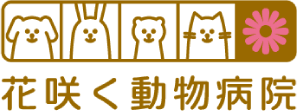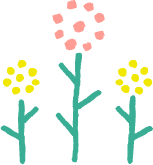認知症の症状・治療・予防・介護を徹底解説
高齢犬が増える近年、「犬の認知症」という言葉を耳にする飼い主さまが増えています。
「夜中に急に鳴くようになった」「同じ場所をぐるぐる回る」「トイレの場所を忘れてしまった」など、これまでと違う行動に戸惑う飼い主さまも多いでしょう。
この記事では、症状・原因・治療法・予防法・介護のポイントをわかりやすく解説します。
目次
認知症とは?高齢犬に増える脳の老化による病気
犬の認知症は、正式には「認知機能不全症候群(Cognitive Dysfunction Syndrome:CDS)」と呼ばれ、脳の老化によって記憶力や判断力が低下する病気です。
特に10歳以上の高齢犬のうち約3割が何らかの認知症症状を示すと報告されています。
人のアルツハイマー型認知症と似た仕組みで進行し、早期発見・早期治療がとても重要です。
認知症で見られる主な症状
認知症の症状は初期・中期・末期で変化します。
早期に気づくためには、日常の小さなサインを見逃さないことが大切です。
初期の症状
-
名前を呼んでも反応が鈍くなる
-
散歩ルートやトイレの場所を忘れる
-
夜に落ち着かず歩き回る
-
食欲や睡眠リズムが変化する
中期の症状
-
家族の顔を認識できなくなる
-
鳴き声が増え、特に夜鳴きが目立つ
-
反復行動(同じ場所をぐるぐる回る)をする
-
トイレの失敗が増える
末期の症状
-
食事や排泄の自立が難しくなる
-
ほとんど寝たきりになる
-
周囲の刺激への反応が乏しくなる
認知症の原因 ― 脳の老化だけではない?
犬の認知症の主な原因は脳の加齢変化ですが、それ以外の要因も影響します。
-
脳の血流低下
→ 酸素や栄養が脳に届きにくくなり、神経細胞がダメージを受ける。 -
活性酸素による細胞の酸化
→ フリーラジカルが神経細胞を老化させ、記憶力が低下する。 -
遺伝的要因
→ 柴犬などは発症率がやや高いとされています。 -
環境的ストレスや運動不足
→ 刺激の少ない生活や孤独も、脳の働きを低下させる要因となります。
犬の認知症の診断方法
動物病院では、問診・行動観察・血液検査・画像検査を組み合わせて診断します。
-
問診:いつから、どのような症状が出ているかを詳しく確認
-
神経学的検査:反射や歩行、姿勢をチェック
-
血液検査:甲状腺機能低下症など、似た症状を示す病気を除外
-
MRI検査:脳腫瘍や脳梗塞などとの鑑別
犬の認知症の治療方法 ― 症状を和らげ、穏やかに過ごすために
認知症は完全に治すことが難しい病気ですが、治療により進行を遅らせ、生活の質を保つことは可能です。
生活環境の工夫
-
室内を明るく保ち、昼夜の区別をつける
-
滑りにくいマットを敷いて安全を確保
-
毎日同じ時間にごはんや散歩を行い、生活リズムを安定させる
食事療法
-
DHA・EPAを含むフード
-
抗酸化物質(ビタミンC・E・βカロテン)を多く含む食材
-
シニア犬用の栄養バランスを考えたフード選択
認知症を予防する方法 ― 毎日の習慣が鍵
予防は「脳に良い刺激を与えること」が基本です。
-
日々の散歩と適度な運動
→ 嗅覚や足腰を刺激し、脳の血流を維持する。 -
飼い主とのコミュニケーション
→ 声かけ・スキンシップが安心感と脳刺激になる。 -
知育トイや新しい遊びの導入
→ おやつを探すパズルトイなどが脳トレになる。 -
バランスのとれた食事
→ DHA・EPA・抗酸化成分を日常的に摂取。
香芝市のように自然が多い地域では、季節ごとに散歩コースを変えるだけでも良い刺激になります。
「見慣れない道」「新しいにおい」は、脳を活性化させる最高のトレーニングです。
認知症の介護 ― 家族全員で支えるために
認知症の進行により、介護が必要になることもあります。
介護の目的は「犬と飼い主がストレスなく過ごすこと」です。
介護の基本
-
寝たきりの場合は体を定期的に動かしてあげる
-
トイレの失敗に備えて吸水シートを利用
-
夜間の徘徊にはサークルやクッションで安全確保
-
鳴き声対策には柔らかい照明や音楽を活用
飼い主のメンタルケアも大切
介護が長引くと、飼い主の心が疲れてしまうことがあります。
無理をせず、動物病院や介護サービスを上手に利用することも大切です。
当院では「介護相談」や「在宅ケア指導」も行っており、家庭に合った支援方法を提案しています。
認知症の動物との暮らしで気をつけたいこと
-
怒らないこと:行動は病気の症状。叱っても改善しません。
-
危険を減らす:段差・階段・家具の角などはクッションで保護。
-
ルーティンを崩さない:環境の変化は不安を強めます。
認知症の犬は、昔のように反応しないことがありますが、
飼い主の声やぬくもりを感じる力は最後まで残っています。
「今日も一緒に過ごせた」という時間を大切にすることが、最高の治療です。
まとめ ― 認知症は早期発見・継続ケアが鍵
認知症は珍しい病気ではなく、誰にでも起こりうる老化の一部です。
しかし、早期発見と適切なケアによって進行を遅らせることができます。
-
日々の様子を観察し、小さな変化に気づく
-
症状が疑われたら早めに動物病院を受診する
-
生活環境・食事・薬・運動をバランスよく整える
香芝市や近隣地域で犬の認知症についてお困りの飼い主さまは、
ぜひ一度「花咲く動物病院」にご相談ください。
犬の気持ちに寄り添い、穏やかなシニアライフを一緒にサポートいたします。
🐾おわりに
認知症の愛犬と向き合う時間は、決して「悲しい日々」ではありません。
飼い主さまが声をかけ、撫でてあげることで、安心し穏やかに過ごせます。
毎日のケアが「愛情のかたち」となり、きっと愛犬の心にも届いているはずです。